
日本酒造りのデジタル化はどう進む?伝統産業における「職人の聖域」と「データの価値」
こんにちは。「デジタル決済の未来をツクル」ディーカレットDCPのハナエです。
さまざまな分野で活躍されるゲストをお招きし、デジタル通貨やデジタル社会、Web3技術の未来を探る本シリーズ。今回のお相手は西堀哲也さんです。
西堀さんは東京大学文学部哲学科を卒業後、都内のシステム開発会社へ就職。ERPシステムの開発エンジニアとして経験を積んだ後、2016年に家業である西堀酒造株式会社へ入社されました。
現在は西堀酒造の6代目蔵元として、伝統的な酒造りを大切にされる一方、IoTを組み合わせた温度管理システムの自社開発、透明化した発酵タンクにLEDを照射して味を変化させた日本酒「ILLUMINA」(イルミナ)の商品化など、最先端技術を活用した酒造りと酒蔵のDXに取り組まれています。
酒造という伝統産業でデジタル技術はどういった役割を果たすのか。酒蔵のDX、酒造りのデジタル化はどこまで進むのか。じっくり話をうかがいます。
酒蔵というミステリアスな空間と後継者としての「納得感」
時田一広(以下、時田):本日はよろしくお願いいたします。西堀さんは老舗の酒蔵の6代目としてご活躍されていますが、子どもの頃は酒蔵という環境でどのように過ごされていたのですか?
西堀哲也(以下、西堀):知らない人への挨拶などは結構厳しくしつけられていたと思います。それから酒蔵には冬のあいだ蔵人(くらびと:責任者である杜氏のもと酒造りに携わる職人)が泊まり込み、早朝から作業するのですが、外から中の様子は見えません。子どもながらに、何となく入ってはいけない空間のように感じていました。
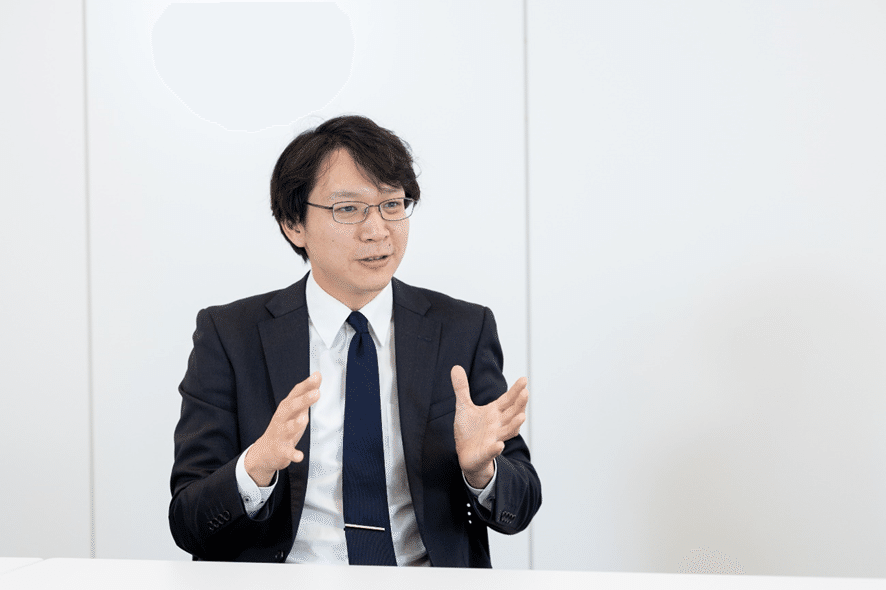
時田:家業でありながら、どこかミステリアスな雰囲気を感じとっていたんですね。
西堀:そうですね。職人を中心に回っている世界というか。酒蔵の中は暗いですし、ちょっと怖さもありました。
酒造りそのものについて詳しく知ったのは20歳を過ぎてからです。それまでは夏休みや冬休みに瓶詰め・箱詰めなどの軽作業を手伝っていたものの、日本酒の製造、酒造りの現場のことは知りませんでした。


時田:家業を継ぐのは、酒造会社では慣習のようになっているのですか?
西堀:私の場合、大学で自分の好きな勉強をさせてもらったということもあったので、逆に酒蔵という自分のルーツというか、環境から逃れられない必然があったのかなと。
先代から「継いでほしい」と直接言われたわけではないのですが、自分のルーツを大切に、一種の使命感をもってやっていった方が納得感があると自己理解しました。いま思うと、あらかじめそうなるように乗せられていたような気もしますが(笑)。
どれも正解という奥深さ。最新研究でも解明されない醸造の世界
時田:家業を継がれてからは、温度管理システムの自社開発やLEDを使った発酵酒の商品化など、西堀酒造さんの事業をどんどん多角化、拡大されていますよね。
西堀:それほどでもありませんが、いろいろ新しいことに取り組んでいるベースにはやはり、「いまのままではいけない」という危機感があります。私は大学を出てから別の業種を経て酒蔵に入ったということもあって、少し客観的な見方をすると、酒蔵がこれからずっと同じことだけをやり続けていくのは難しいだろうと感じていました。
それから、酒造りに携わっていくうちに、自分自身、いろいろな面白さを感じるようになりました。
私は前職がエンジニアなので、ある意味ロジックで動く部分があるのですが、生き物を扱う醸造の世界では、同じ温度で管理していても上手くいったりいかなかったりします。不思議な要素、最新の研究でもまだまだ解明されていない部分がとても多いんです。論理化できていない部分が多いということは、それだけ可能性があるということだと思います。

時田:飲食店でお酒をいただくと、お店の方からいろいろとご説明をいただきますよね。それで私も興味を持ち始めているのですが、酒造りは想像以上に奥深い世界なんですね。
西堀:そうですね。手をかけようと思えば、それこそ無限にかけられます。それぞれの酒蔵、それぞれの職人によって千差万別のやり方があって、ある意味ではそのどれもが正解だと言えるのかもしれません。
酒蔵DXの進め方。デジタルで当たり前を変えるということ
時田:その酒蔵のDXを進めるにあたって、従業員の方々から反対、反発の声などはなかったのですか?
西堀:手作業をデジタル化すると、これまで当たり前にやってきたことが大きく変わります。だから当然と言えば当然なのですが、入社1年目にした提案は「それは聞かなかったことにする」という感じでほとんどスルーされてしまいました(笑)。
そこで大切だと気づいたのは、やはり現場を知ることです。当時は蔵に入ってまだ間もない時期だったので、まずはこれまで蔵人の方々やってきたのと同じレベルの作業、もしくはそれ以上の作業を実際に自分でやってみて、現場の方の気持ちに寄り添うようにしました。そうしないと新しいことを提案する資格もないなと。

そこで入社から3年ほどは1人の蔵人として朝から晩まで全作業をやらせてもらいました。そのうえで「こんな方法もあります」という形で自分がつくってみたもの、用意してみたものを見せ、この方法でやれば、今まで当たり前にやってきたことがより簡単になるし、情報を共有できるし、家に帰ってからも現場で気になっていたことをチェックできるようになると伝えました。
それで少しずつ信頼関係を築くことができてきたと思いますし、最初から一気にガラッと変えようとしても、おそらく難しかったと思います。
瞬間の判断が品質を左右する。酒造りの現場におけるデータの価値
時田:実際に蔵人の仕事を経験し、現場を理解したことによって西堀さんご自身のアイデアや考え方、提案に変化はありましたか?

西堀:それは大きく変わったと思います。例えば、朝の仕込み作業は分単位で進みます。蔵人の手には醪(もろみ)が付きますし、その場ではスマホやPCを起動してデータを記録するより、手元のペンと紙でぱぱっとメモするほうが合理的なんです。
それからデータを取ったとしても、オフィスワークなどと同じようには活かされないということもわかりました。酒造りの工程における「ここまで温度がこう推移しているから冷却を強めよう、弱めよう」といった諸々の判断は、あくまで個人の頭のなかでその瞬間、瞬間に下され、経験として蓄積されていきます。
データがあれば、その場でデータを見るという習慣は生まれますが、それを判断材料にしたり、後から履歴を見返すといったことは、結果論の分析でしかないので、少なくとも日々動いている酒造りの現場ではほとんどありません。データそのものの価値、利用目的が違うので、膨大なデータを集めてひたすら統計処理すればいいというわけではないんですね。
時田:まさに職人の聖域ですね。

西堀:そうですね。機器を導入する際にもそういった面の難しさはありました。現場に電子機器を導入するといっても、酒蔵では目に見えない微生物を扱っているので、蔵人からすると仕組みや影響がよくわからないものは入れたくないんです。
その点で抵抗はありましたが、DXを進めるにはWi-Fiを蔵内に入れておかないと何もできないので、そこは説得しました。導入までに3年、4年かかったと思います。
ちなみに、なぜそれができたかというと、事業用として国の補助金の採択を受けたからです。国からお墨付きをもらうことで、必要な機器を導入していくことができました。何らかの新しい提案をして、それを受け入れてもらうためには、第三者、外部と何らかの結びつきがあると進めやすいのかなとは感じています。
時田:電子機器の導入などによって酒蔵DXが進んだことにより、従業員の方々の反応は変わりましたか?
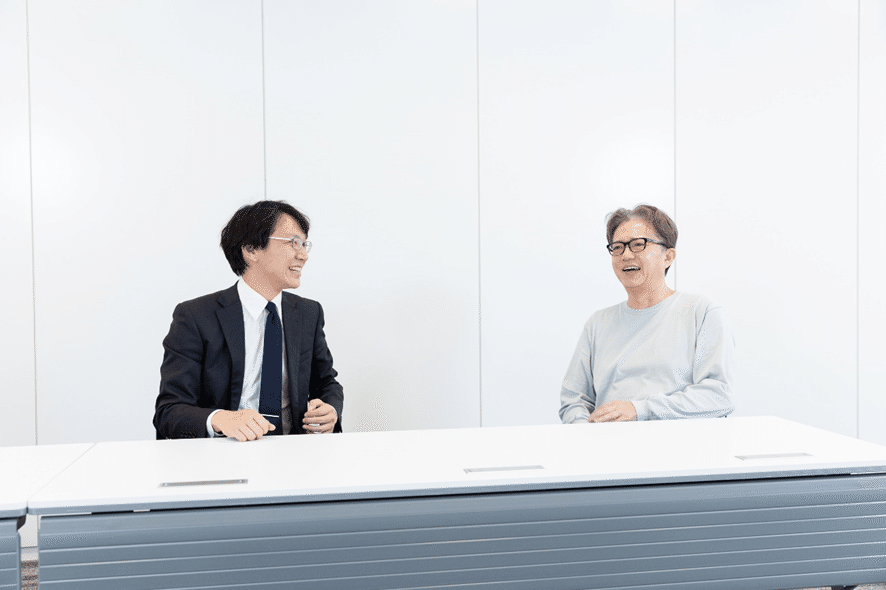
西堀:それはもう「とても使いやすい」と(笑)。最初の頃の抵抗はいったい何だったんだろうと思いますが、逆に言えば、最初の頃はそこまで話せない、簡単に受け入れてもらえないお互いの壁があったのかなと思います。
時田:心を開いてもらったという感じなんでしょうか。
西堀:そうですね。人間的な部分というか、納得感、感情の部分はやはり結構大きかったと思います。
ー次回はデジタル化が進むなかでなお残る人の手仕事の意義や、西堀酒造さんの今後の事業についてさらに詳しくお話をうかがっていきます。

